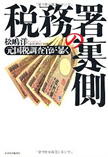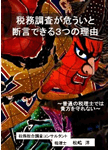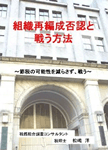![]() 2016/03/17 12:23 PM
2016/03/17 12:23 PM ![]() NEWS
NEWS
行為計算否認の考え方
行為計算否認は法律を作る側を想定する
税には、行為計算否認規定という強硬的な制度がある。 ごく簡単に言えば、法律上は問題ない節税でも、行き過ぎ という場合には税務署の権限で否認できるという規定。 簡単に言うとこうなるが、実務はそうは回らない。何を以て 行き過ぎた節税になるのか、不明確極まりない。 こういうわけで、学者が判例を見ながらいろいろと指摘しているけど、 根本的な部分は分からない。根本的な部分が分からないから、 どのような場合に否認されるのか、理解できない。 そもそも、この規定は行き過ぎた節税を否認する、という理解は 正確ではないと考えている。重要なことは、そのような節税を、 法律を作る側が想定していたかどうかである。 想定できるような課税逃れについては、きちんと法律に書く。 寄附金課税や移転価格税制はその典型だろう。 一方で、想定できなかった課税逃れについては、それを許せるか どうか、社会常識に照らして判断することになる。 ここで重要な基準は、以下の二つ。 1 当然に想定できるものかどうか 2 法律に書くことができるかどうか 1について。想定できる課税逃れについて法律に書いていない。 これは国の怠慢であり、納税者に非はない。 例えば、法人税ではないけど事業者免税点。二年前の売上が 1千万円以下なら消費税がかからない。こんな法律があれば、 二年で別会社を作る 免税となる会社に外注費を払い、節税する こんなことは誰でも思いつくこと。それがまずいなら、 きちんと条文に書くべきだ。 2について。法律を書く場合、複雑な取引を防止するための 条文は非常に書きにくい。複雑な取引であるため、それを 否認するための要件もたくさん書かなければならないからだ。 こうなると、条文の文字数が膨大になるし、否認規定が適用 されないか、逐一確認しながら処理する必要があるため納税者 も困ることになる。 一方で、シンプルな取引を防止するための条文は書きやすい。 時価で取引しなければならないとか、役員報酬を払いすぎては いけないとか、こういうものは簡単に条文に書ける。 つまり、条文を書く側の気持ちになって課税逃れを考えると いうこと。この気持ちを判断するのは、法律ができた趣旨を 見るよりほかにない。
 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。@yo_mazs
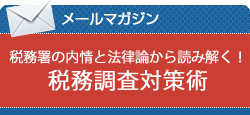
-
「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない
「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ... -
社会保険料と非常勤役員
税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的にはケースバイケースの 判断になりますが、こういう...
- NEWS (231)