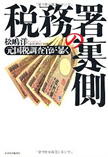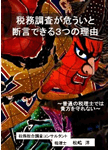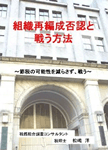![]() 2016/05/23 9:36 AM
2016/05/23 9:36 AM ![]() NEWS
NEWS
税務署から連絡がないのはなぜか?
調査が終わったのに連絡がない
調査件数が減っているなどと問題視しておきながら、全くもって 矛盾するのだが、実地調査が終わっても、調査結果の発表は非常に 遅いことが通例である。
以前立ち会った税務調査、実地調査がなされたのが8月末。 結果説明があったのが、12月中旬。 4月近く待たされているのに、指摘内容は従来と変わらず、
すいません、今日が締めなので 至急修正申告を準備してください
などと、税理士に言われても、会社に許可を取る必要もあるので、 到底無理な話。しかし、空気の読めない税務署の担当者は、 このような指導をすることが多い。
12月なので、まだ許せる話。 ひどいと、年明けに行われる税務調査については、異動時期である 7月の直前まで、連絡がないことも珍しくはない。 引継ぎはよほどのことがない限りやりたくないので、調査官ももう少し 頭を使って調査を終わらせるべき、と思うところ。
この点、実は私の現職時代(平成15~19年)からも、 結果の発表が遅いことは通例だった。現在ほどひどくはない、 というだけで。
連絡が遅くなる理由は
①反面調査などの補完的な税務調査を行っていること ②幹部職員との日程調整に戸惑っていること ③指摘事項を説得させる根拠に乏しいため先延ばししていること
の3点がある。
①については言うまでもない。会社で行った税務調査において、 何か不正の「端緒」を発見した場合
内容を解明するために取引先に反面調査を実施する 市役所などにお尋ね文書を発送する
このような補完的な税務調査(補完調査)を行っていれば、 処理に当然時間がかかってしまう。
従来、不正が見込まれるような場合を除き、反面調査はほとんど やらなかったが、理由附記の影響もあって、軽い間違いでも 反面することも多いため、日数は長くなりがちである。
②について。税務署内部では、増差所得や追徴税額に応じて、
重審(「重要事案審議会」)と呼ばれる署長や副署長などの幹部職員の決裁
が必要になることがある。 普通は統括官の決裁で方がつくのだが、優秀な調査事績を残した職員のお披露目 を兼ねてこういう報告会をやる。
重審には、幹部職員はもちろんのこと、審理担当や統括官も出席するため、
日程調整が大変になる
のだ。
さらに面倒臭いことに、この重審には、署長向けと副署長向けの 2つがあり、事績が大きい場合になされる署長向けとなると、
事前に副署長に事案を報告する(「予備重審」)
もやるのだ。 署長はいちばん偉い人だから、その前の偉い人である副署長に あらかじめ許可を得ておく、という名目でなされるわけだが、 もちろん
深い検討をするわけでもない、縦割りの弊害 であり、実地調査が終わっても徒に時間が経過して しまうことも多い。
もっとも多いのは③。 納税者や統括官を説得するに当たり、法律的にグレーな部分は、 税務署の書籍などを活用して調べなければならない。 しかし、この調べる作業は非常に面倒ですから、 後回しにすることがほとんどであり、調べたところで
(法律ではなく)書籍の著者の見解にすぎない
から、説得力がある話にはならない。
結果として、調査官の考えとしては、
もう少し時間をとれば、より有効な説得材料が浮かぶかもしれない
といった淡い期待も込めて、先延ばしにすることが 多々あるため、連絡は遅くなる。 本来なら、直属の上司である統括官が進捗管理を厳密に行うべき なのだが、調査官の仕事はほとんど個人プレイであり、
統括官も副署長等から尻を叩かれない限り、原則として 動かない
わけで、無意味な時間が税務調査には発生する。
税務調査の結果連絡が遅くなると、
何か重大な間違いがあるのでは?
と思われますが、重大な間違いであれば、
早く連絡が来る
ことが多い。 重大な間違いを見つけると、
調査官は鼻高々で早く決着して上司に褒められたい
と思うことが通例だからであり、何より、早く報告する ということは、
人事の目につきやすい
ことから、調査官にとってはうれしいことなのだ。
このため、連絡が遅くなってもそれほど 心配する必要はなく、のんびり構えておくと いいだろう。
 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。@yo_mazs
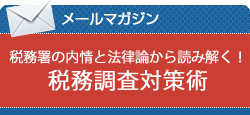
-
「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない
「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ... -
社会保険料と非常勤役員
税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的にはケースバイケースの 判断になりますが、こういう...
- NEWS (231)