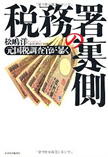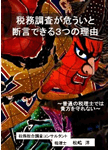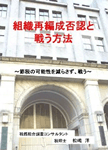![]() 2016/09/01 11:18 AM
2016/09/01 11:18 AM ![]() NEWS
NEWS
持株会社スキームに国税が厳しくなった?
銀行提案の自社株提案の否認例が相次ぐ
産経新聞の記事にあったショッキングな内容。 http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html 安易な節税を許さない、という強権的な課税が復活していると言える。 契機としては、ヤフー事件でビジネスリーズンがあっても否認できる、 という画期的な判断がなされたことが原因である。 個人的な意見を申し上げると、租税回避の否認に対しては、以下の ポイントで見るのが最も納得できると考えている。 ① その取引が、立案者が予測できなかったものか ② その取引を予測できるにしても、条文で書けないほど複雑なものか ①については、時代の変化などで見ればいいだろう。想定できないが 否認されるべき節税はあるのであり、こういうものを租税正義に照らして 否認するのがあるべき姿だ。 ②については、細かすぎるものは条文に書けないので、取引が複雑かどうかで 見ればいいと思う。 ①にしても②にしても、重要なのは法の趣旨と租税正義という常識であるが、 困るのはこの両方に関する知識が国税にないということだ。
法の趣旨も学ばないし、安易な節税がダメなことが租税正義と解釈しているため、 ビジネスリーズンといった理屈から否認しようとし、それで反論されれば こんなものは関係ない、といった形で責任逃れをしようとするから 話が複雑になる。 あくまでも、法律を作る権限は国税が持っているのだから、国税に非があるため 税逃れが生じているか、そこが問われるべきだろう。 法を悪用して税逃れするのがダメなら、法律を改正すればいいだけの話。 それができていないのが、国税の責任か、はたまた納税者の責任か。 問われるのは、国税が悪用を予測できたか、予測できても法技術上 書けないので、包括否認でやるしかないと判断したのかそれだけである。 特に、株の評価については財産評価基本通達という欠陥通達が基礎に なっているわけで、その欠陥通達を何とかまともなものにするのが 国税の役目だと思う。
 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。@yo_mazs
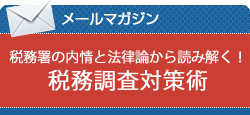
-
「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない
「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ... -
社会保険料と非常勤役員
税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的にはケースバイケースの 判断になりますが、こういう...
- NEWS (231)