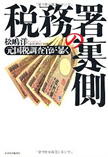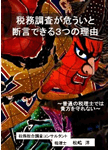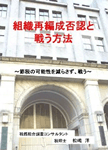![]() 2014/01/30 9:00 AM
2014/01/30 9:00 AM ![]() NEWS
NEWS
保証債務履行の特例
保証債務履行に係る課税の軽減
非常に有名な所得税の特例。保証債務を履行したにもかかわらず、 主債務者に求償できないのに、資産を手放すのは酷、ということが 勘案されて設けられた制度。 この点、非常に大きな問題になるのが、 主債務者から求償見込みないときに、債務保証しても適用がない という点。この点、条文を確認してみると、
の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)
があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないことと
なつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の
金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する
回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。
このうち、「行使することができないこととなった」という解釈が問題になるという。
できなくなった、ということには、後発事象による、という意味が込められているから、
明らかに求償できない主債務者を保証してもダメ、という結論が導かれるという。
しかし、ここまで解釈できるか、というと大いに疑問。「できなくなった」というのは、
当初の見込みというよりも、事実関係としてそうなった、という意味に捉えるのが
普通と思う。
何より、こう解釈できるようじゃないと、条文の解釈は非常に困難になる。
条文と格闘する、ことも必要であることは事実だが。
結論としては、解釈論というよりも、趣旨解釈の側面が大きいだろう。
その上で、本制度のロジックは、判例で認められた、というのが
本当のところと思う。
趣旨解釈は、税法では限定的とすべきだが、困ったことに、当局は
安易な節税を防止するため、往々にして使ってくる。結果、裁判で
認められると、条文がより怖いものになってしまう。
裁判で認められたから、という理屈があると、現行の条文で
大丈夫、という結論になり、改正も行われない。
 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。@yo_mazs
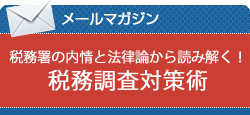
-
「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない
「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ... -
社会保険料と非常勤役員
税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的にはケースバイケースの 判断になりますが、こういう...
- NEWS (231)